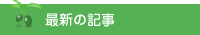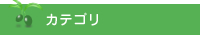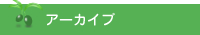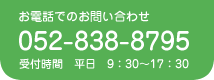
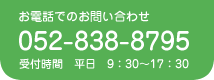

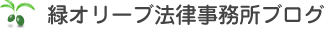

先日、とある公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいた際にもそうしたのですが、「予備的遺言」と呼ばれる記載方法があります。
例えば、遺言者の法定相続人は二人の子A・Bであり、A・Bにはそれぞれ子(遺言者からみれば孫)a・bがいるとします。遺言者は、同居するAに自宅不動産を相続させる、という遺言を作成していました。ところが、不幸にも遺言者よりも先にAが死亡してしまいました。
この場合、おそらく、遺言者としては、Aに相続させようとした自宅不動産について、その子(孫)aに相続させたいと考えるでしょう。
しかし、そのことを遺言に記載しておかないと、当然にはaに相続させることにはなりません。遺言者よりも先にAが死亡してしまった場合、作成されていた遺言のうち、「Aに相続させる」とした部分だけが、Aがいなくなってしまったことで無効となるからです。ゆえに、Aに相続させるつもりだった自宅不動産については、相続人間(a・B)であらためて遺産分割協議をすることになります(原則として、法定相続分どおり(この事例ではa・B半分ずつ)に分割することになります。)。
このような場合に備え、遺言で、①「遺言者は、その有する自宅不動産をAに相続させる」という条項(主位的な遺言)とともに、②「遺言者は、Aが遺言者より先に又は遺言者と同時に(※)死亡したときは、Aに相続させるとした財産をaに相続させる」という条項(予備的な遺言)を記載しておくわけです。
(※)Aが遺言者と同時に死亡したとき(同一の事故や災害で死亡したときなど)も、法的には、Aが遺言者よりも先に死亡したときと同様に、「Aに相続させる」とされていた部分が無効になります。
しばしば見られるのは、子のいない夫妻が、自分たちが亡き後、遺産を各きょうだいが相続するくらいなら、しかるべき慈善団体や福祉施設に寄付したい、とお考えの場合です。
①主位的遺言としては、他方(夫は妻、妻は夫)にすべて相続させる、としつつ、②他方が遺言者より先に又は遺言者と同時に死亡したときは、団体Xに遺贈する、といった予備的遺言を作成することになります。
ご自分の希望を適切に反映させるために、遺言書作成についても、是非弁護士にご相談ください。(浜島将周)
― 緑オリーブ法律事務所は名古屋市緑区・天白区・豊明市・東郷町を中心にみなさまの身近なトラブル解決をサポートする弁護士の事務所です ―